少子高齢化とは何か?
今日は「少子高齢化」について、分かりやすく話していきたいと思います。初歩的な知識から、俺自身の考えも交えながら整理します。
つまり、“今の日本がどんな状況にあるのか”を正しく知ることが第一歩です。
2024年時点での日本の総人口はおよそ1億2,410万人。1年間で約86万人が減少しています。
これは和歌山県の人口が丸ごと消えるほどの規模です。つまり、都道府県ひとつ分の人が1年でいなくなっているということです。
国立社会保障・人口問題研究所によると、2040年には1億1,200万人前後まで減る見通しです。しかし、実際はそのスピードが予測を上回っており、すでに数年前倒しで到達しつつあります。
つまり少子高齢化は「加速」している。
生産年齢人口の減少がもたらす現実
※生産年齢人口=15〜64歳の、社会で働く中心世代のこと。
2024年時点では約7,437万人。しかし2040年には6,200万人台まで減少すると予測されています。
働く人が減るということは、国力が下がるということです。国力とは、GDP(国内総生産)や社会全体の活力を指します。
人が減ると税収が減り、社会保険料は上がる。そして医療・介護費用も増大していく。「稼ぐ力が減って、支えるコストが増える」──まさにこれが現状です。
日本は明治維新以降「ものづくり国家」として発展してきましたが、その根幹を支える人材が減り続けています。ものづくりすら維持できなくなる時代に、すでに入りつつあるのです。
高齢化と出生率の現状
※高齢化率=65歳以上の人が全人口に占める割合。
2024年の高齢化率は約29.1%。つまり3〜4人に1人が高齢者という社会です。
2060年には約40%に達すると言われています。
※合計特殊出生率=1人の女性が一生のうちに産む子どもの平均数。
人口を維持するには2.07人が必要ですが、日本は1970年代から下がり続け、現在は1.20。これは戦後最低です。
結婚しない人が増え、価値観が多様化したことで、「子どもを持たない生き方」も一般化しました。
海外の事例に学ぶ少子化対策
シンガポールでは1988年に出生率1.48、2023年には0.97まで低下。日本と同様、極めて厳しい水準にあります。
スウェーデンでは、女性が働きやすい環境を国全体で整備。出産後は夫婦で480日間の育児休暇を取得でき、給料の約80%が補償されます。
結果、90%以上の親が育休を取得し、専業主婦はわずか1%以下。育児をしてもキャリアを失わない社会構造が整っています。
フランスでは「結婚=子ども」という価値観がなく、結婚していなくても子どもを持つのが普通の文化。早い段階で多様な家族の形を受け入れ、出生率を1.9前後まで回復させました。
どの国にも共通しているのは、「働き方」や「家庭の形」を柔軟に受け入れる姿勢です。
日本はまだ「変化を恐れる社会」ですが、国任せではなく企業や個人が自発的に社会課題に取り組む必要があります。
俺なりの結論
俺の会社も、少子高齢化に対して根本的な対策を意識して動いています。ただし、俺は少子高齢化そのものを悪いとは思っていません。
問題は「数字」ではなく、その背景にある人間的課題です。孤独・恋愛・お金・自己肯定感──。それらを解決すれば自然と「家庭を持ちたい」と思える人は増える。
結婚したくない人はそれでいい。でも結婚したいのにできない人、恋愛したいのに踏み出せない人がいる。その状態を放置するのは、社会として間違っています。
俺たちは、そうした日本の課題を解決しつつ、「なりたい自分になれる社会」を作りたい。
少子高齢化は“結果”であって、“原因”ではない。人が幸せになれば、社会も豊かになる。それが俺の信念です。

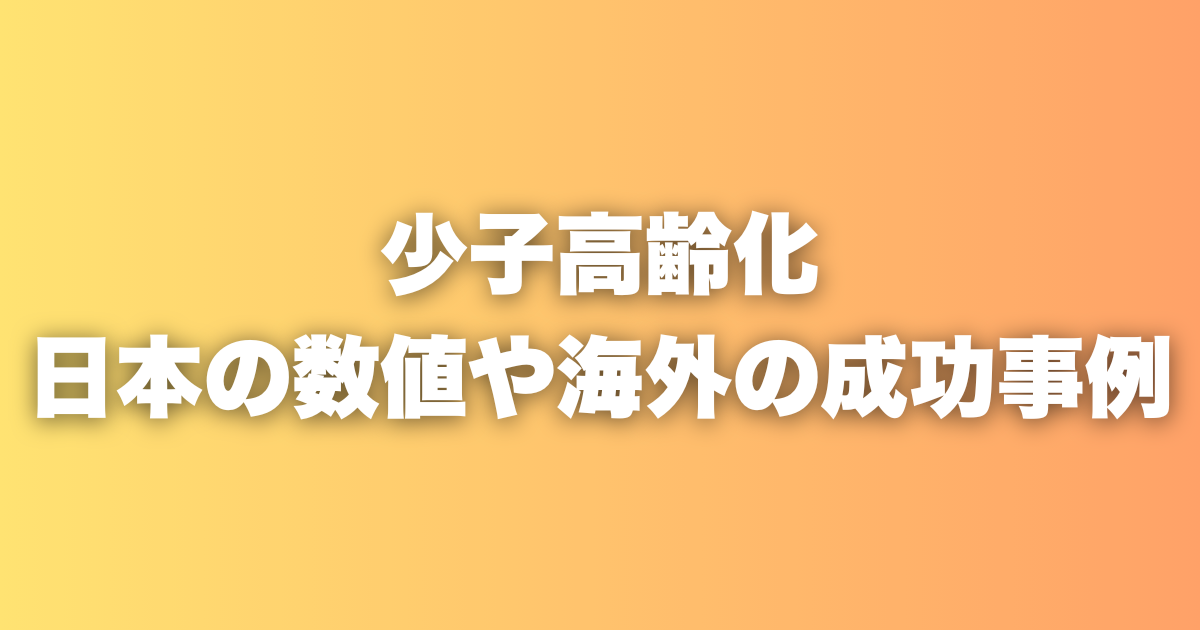
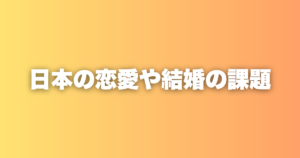

コメント